2017年11月24日に、千葉県立袖ヶ浦高校 情報コミュニケーション科の平成29年度課題研究発表会に参加してきました。昨年度の課題研究発表会には参加できなかったので、2年ぶりの参加になりました。袖ヶ浦高校の生徒たちは一人1台のiPadを持っていますが、情報コミュニケーション科の科長である永野直 先生は、「一人1台のiPadを活用すること自体が目標ではない。ICTと社会をつなげて創造的に課題を解決するのが目標」と言います。この「社会で創造的に課題を解決する」という目標へのステップとして、課題研究発表会は存在しているのだと思います。

永野先生は、「課題研究では、iPadを使え」というようなデバイスの指定はしておらず、生徒たちは、iPadだけではなく、学校のPCや自分のスマートフォンやPCなども使って課題研究を行ったそうです。袖ヶ浦高校の情報コミュニケーション科では、先生方は「(一人1台のiPadを)自分たちの中で目的をもって使え」と言ってきているそうです。この課題研究発表会は、目的を持ってiPadを始めとするICT環境を使ってきた生徒たちの「3年間の集大成とも言える」と永野先生は言っていました。

課題研究発表会の資料などは、サイトにアップされており、参加者には無線LAN環境が提供され、URLが伝えられました。

永野先生は、「(このサイトで情報を見るために)来校者が生徒の前でスマホを使うのも、この学校では全然かまいません」と言っていました。こうして資料を配布せずペーパーレス化しているのも、ICT活用のひとつであり、学校としてICT環境を日常使っている証拠だと思いました。
実はこうした活用をしている学校も全国で見るとそう多くはありませんので、こうした試みは続けてほしいと思いました。
課題研究発表会は、90分の間に高校2年生と高校3年生が同時に発表をします。1階の会議室で、3年生の6グループがポスターセッションを行います。それぞれのグループの代表が、最初に見どころを説明に来てくれました。
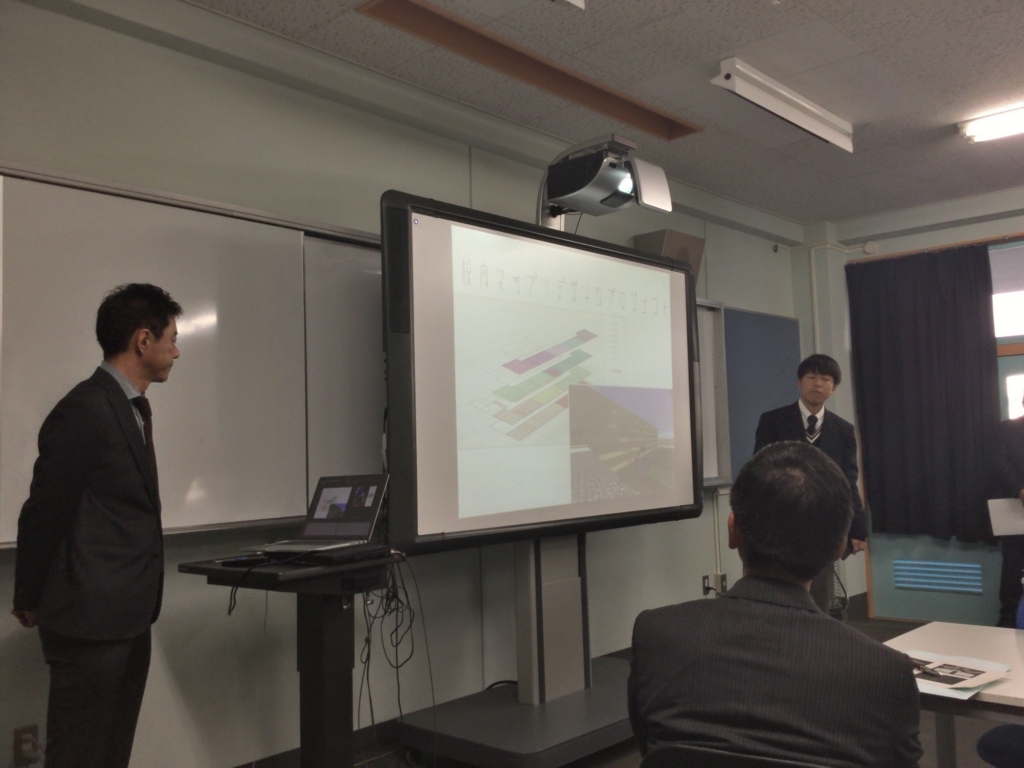
また、2階の第一コンピュータ室で、2年生の全員がScratchを使って作ったプログラミングの作品を40人が一人1作ずつ展示するそうです。
今回の課題研究発表会には、卒業生も見に来ていました。また、1年生40人も、先輩たちの発表や展示を見ていました。そして、熱心にメモをとっていました。1年生は、先輩たちの発表を見ることで、先輩たちへのあこがれを抱くとともに、自分たちが研究と発表を行うときの規準をもつことができるのだと思います。こうした縦での繋がりが、袖ヶ浦高校の課題研究発表会の伝統を作っていくのだと思います。

No.2に続きます。
blog.ict-in-education.jp
(為田)