2025年4月24日に東京ビッグサイトで開催されているEDIX東京へ行ってきました。EDIXはたくさんのセミナーやプレゼンテーションを聴き、最新情報や授業事例などを知ることができる場であり、「教育の情報化」を目指す仲間たちと会える場だと思っています。
STEAM JAPAN 編集長・井上祐巳梨さんのセミナー「STEAM・探究最前線 ― 国内&海外最先端事例から紐解く、これからの教育の在り方」に参加してきました。タイトル通り、国内外のたくさんの事例を紹介してもらえて、セミナーを聴きながらたくさん検索していろいろな学校のことを知れました(夢中になって聞き逃したパートもたくさんありますw)。
井上さんが紹介してくれた学校と、最後の質疑応答でとった自分用のメモを共有したいと思います。
One Stone
アメリカ・アイダホ州にあるNPO法人One Stoneが運営している学校Lab 51。高校生が自ら学校運営に関わっているそうです。リセマムさんの取材レポートがありました。
One Stoneのサイトを見ると、PBSで紹介されている動画がありました。
DESIGN 39 CAMPUS
アメリカ・カリフォルニア州にあるDESIGN 39 CAMPUS。こちらは、井上さんが編集長を務めるSTEAM JAPANのSTEAMレポートで訪問レポートが出ていました。
STEM Learning UK
STEM Learning UKのサイトへアクセスすると、バナーに「Primary」と「Secondary」のタブがあって、そこからさまざまなリソースを見ることができるようになっています。
こういう、「リソースを共有する」というのはとても大事だと思いつつ、このサイトで公開されているリソースが、各学校でどんなふうに使われて、リーダー的な先生からすべての先生にどう広がっていくのか、というところにすごく興味があるな、と思いながら見ました。
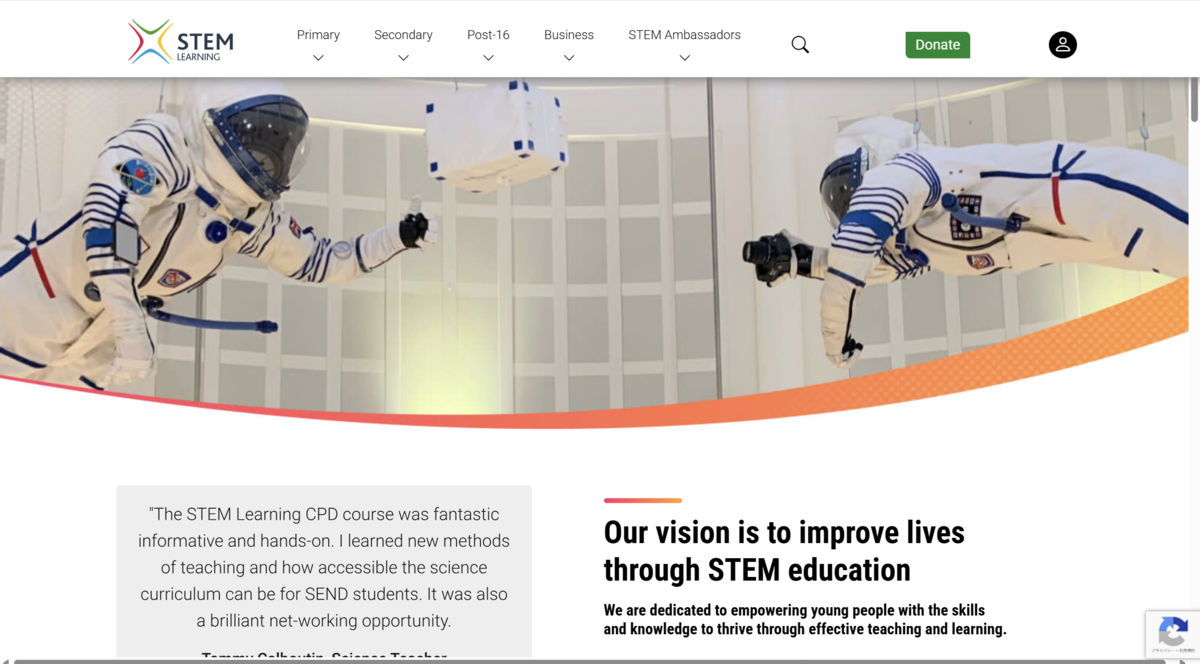
渋谷区:探究「シブヤ未来科」ポータル
日本からは、渋谷区が作っている探究「シブヤ未来科」ポータルが紹介されていました。探究は、社会課題に結びついて子どもたちの気持ちをドライブしていくのが大事なので、こうしてデジタルで企業と学校を繋げて、分野横断的な学習ができるようにしていく、というのは大事な施策だと思います。
探究の探求の事例をみんなでシェアしていくシステムが大事だと思います。このポータルが、探究の事例を渋谷区内で横展開するための仕組みとして学校にどれくらい根づいているのかとか、先生が実際にどんなふうに使っているのかとか、知りたいなー、と思いました。

大田区:「おおたの未来づくりポータル」
渋谷区と同様に、大田区も「おおたの未来づくりポータル」を作っています。大田区では、「笑顔とあたたかさあふれる未来を創り出す力」の育成を目指して、小学校5年生と6年生で独自教科「おおたの未来づくり」を実施しているそうです。
企業などの専門家と繋がることができるようにポータルが用意されています。先生方が教えられなくても、そういった人たちと繋がることが大事です。

大分県:OITA STEAM PLATFORM
大分県では、「OITA STEAM PLATFORM」を作っています。OITA DATA SCIENCE EXPOなどのイベントも実施されています。
それと、大分県立国東高校も紹介されていました。国東高校は、普通科(進学コースとビジネスITコース)、園芸ビジネス科、環境土木科、電子工業科があり、2024年度からは新たに普通科SPACEコースが加わり、国東市と国東商工会議所と連携して宇宙関連の商品開発をしているそうです。
大分県は、STEAM JAPANでも先進自治体事例として紹介されていました。
steam-japan.com
ファシリテーター赤堀侃司 先生とのやりとりから
一般社団法人 ICT CONNECT21会長・東京工業大学 名誉教授の赤堀侃司 先生がファシリテーターとして、井上さんに質問をしていきます。赤堀先生とのやりとりと、セミナー会場からオンラインで集めた質問への回答という形でやりとりが行われました。
- Q:探究についてどうやったらうまくいく?(赤堀先生)
- 時間がかかる、特に問いの設定の部分に。問いの時間にとにかく時間をかけて、そのあとで先生方にも難しい、専門家が出てこないといけないところが出てくる。そのときに、専門家につなげてあげるという仕組みが必要になる。まだこの仕組みがサステナブルに作られていけば、先生方は現場で問いの設定の伴走者となればいい。
- 専門家とつなぐ仕組みを作ること。企業はCSRの部門が窓口に。
- 「自分で未来を切り拓く、それほど素晴らしいことはない」これが探究のもっている良さ。
- Q:探究の土台に学力は必要?そうすると、授業時間が足りなくないですか?
- 土台に学力は必要だと思う。デジタルを活用して効率化することも必要だろう。
- 「未来の教室」のコンセプト、「知る」と「創る」の往還が大事だと思う。
- いまの子どもたちは「作りたがっている」と思う。
おわりに
セミナーで聴いたことをさらに調べようと思うと、STEAM JAPAN「STEAMレポート」がたくさんヒットしました。めちゃくちゃおもしろくて、つい読むのに夢中になってしまいました(で、セミナーをところどころ聴き飛ばしました…)。RSSリーダーに登録して、これからも勉強させてもらおうと思いました。
(為田)